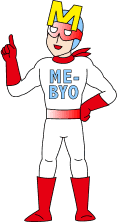災害ボランティア体験談
2025年9月26日
災害ボランティアの活動内容や、活動を通して感じたことを、東日本大震災などで被災地支援を行ってきた神奈川災害ボランティアネットワークの皆さんに聞きました。
災害ボランティアを始めたきっかけ
(司会)活動のきっかけを教えてください。
(齋藤)東日本大震災です。震災時は神奈川にいましたが、以前の職場が東北で友人もおり、何かしなければと友人を訪ねて行きました。その後、仲間とやりたいと思い、神奈川災害ボランティアネットワーク(注釈1)で活動を始めました。
(注釈1)NPO法人神奈川災害ボランティアネットワーク(略称:KSVネット)
(石橋)勤務先で社内向けに救急法を教えていた時期に、旅行で乗った飛行機が乱気流に巻き込まれ、乗客が頭を天井にぶつけ、私の横に落ちてきたんです。その方は気絶してしまい、私は「大丈夫?」と声をかけて。
「この時のために、救急法をやってきたんだ」と思いましたが、実際にことが起こると、何もできないんですね。たまたま乗客に詳しい方がいて、倒れた方は意識を戻しました。その時に、今まで何を教えてきたんだろうと思いました。
これがきっかけで、地元の海老名で活動を始めました。3.11では大きな揺れを感じ、テレビで震災の状況を目にして「何かやらなきゃ」と思いました。何がしたいかはまったく分かりませんでしたが、その思いが、今につながっています。

東日本大震災でのボランティア活動
(司会)被災地支援の内容を教えてください。
(石橋)支援は発災日から行っていて、メインとなったのはボランティアステーション事業です。活動先は岩手県と宮城県で、岩手では遠野市に「かながわ金太郎ハウス(注釈2)」という施設があり、ボランティアは何日でも何か月でも無料で宿泊できました。そこを拠点として、海岸の被災地までバスで往復しました。
(注釈2)かながわ金太郎ハウス:かながわ東日本大震災ボランティアステーション遠野センターの呼称
かながわ東日本大震災ボランティアステーション事業
東日本大震災の被災地の復旧・復興支援のためのボランティア活動の一層の促進のため、2011年4月11日に神奈川県(かながわ県民活動サポートセンター)、県社会福祉協議会、神奈川災害ボランティアネットワーク(KSVネット)の共同事業としてスタート。2013年3月末までに、371台のボランティアバスを運行し、延べ11,330人のボランティアが岩手県、宮城県で活動しました。

どんな作業をするの?
(司会)実際に、どのような活動があるのでしょうか。
(齋藤)震災当初はがれきの撤去が主でしたが、力仕事だけでなく、仮設住宅を訪問してお手伝いするなどのソフト面のボランティアもニーズがあります。「子どもの世話をしてほしい」という依頼もありました。相続や自宅の解体など、財産についての相談事があれば、弁護士や司法書士につなぐサポートもしました。
(石橋)道が整備された少し後に、津波で流された写真や位牌などをすべて拾って、持ち主に返したいという思いから、思い出探し隊(注釈3)を派遣し、回収、仕分け、洗浄作業を実施しました。
(注釈3)かながわ思い出探し隊:2011年4月9日から5月7日まで、陸前高田市、大船渡市へ派遣
(齋藤)また、農業支援や漁業支援もやらせていただきました。
(石橋)漁業支援というのは、海岸で養殖されているカキやホタテの復興のお手伝いで、私たちはとても勉強になりました。
(齋藤)そのほか、活動前に被災地のニーズを把握するための先遣隊や、「東日本を応援 ほしいものリスト」で現地で必要な土のうやスコップの寄付のお願いや、ボランティアバスの応募者を募集する情報班、県内へ避難された方へのお手伝いもありました。

出典:かながわ東日本大震災ボランティアステーション事業25カ月の記録(かながわ県民活動サポートセンター・社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会・特定非営利活動法人神奈川災害ボランティアネットワーク)
人に寄り添うボランティア
(司会)大変なことはありましたか。
(齋藤)震災時の話を聞いて共感し、とてもつらくなることがありました。ですが、私たちが被災された方の話を聞くことで、その方の気持ちが落ち着くことがあります。ですから、ボランティアには「被災された方が話をしたい時は、作業を止めてでもしっかり聞いてください」と、伝えていました。
(石橋)被災された方は、話したことに対して何らかの答えを求めているわけではなくて、私たちのような、関係ない人に話すというのが、わりあいすんなりいけるという気がしました。周りの方も同じように被災されていますので。
(司会)活動は、物理面だけではないということですね。
(齋藤)ボランティアに行って、土ばかり見るなということです。「その方の心へ」という意味で、人を見ましょうと。復興は町の景色のことだけでなく、人間のことなので、接し方に配慮しましょうということです。
(司会)ボランティアメンバーに対するこころのケアやサポートはありますか。
(石橋)岩手では宿泊先で、初日の活動後にミーティングをします。私たちみんな、涙、涙という感じですね。とめどもないほど泣き出しちゃう。活動の中に気持ちがあるんですよね。
(齋藤)つらい気持ちはミーティングで出して、家に持ち帰らないようにしています。
(石橋)宮城は宿泊がないため、帰りのバスで振り返りをします。さまざまな質問が出ますので、私たちスタッフは、疑問を残したままにしないように対応していました。

災害ボランティアは人とのつながり
(石橋)岩手では活動後の夜に自由時間を設け、仲間で話したいことを話して、だいぶ打ち解けることができました。そういったところでつながりができていたので、翌日の作業分担もスムーズに行えました。
(司会)ボランティアをして良かったことはありますか。
(斎藤)少しは地元の復興のお手伝いができたことです。仲間といっしょに活動したときの達成感もありました。また、いろいろなところで経験を積めば、地元にもいかせます。
(司会)活動を継続される方は多いですか。
(石橋)多いです。ステーション事業を機に参加して、ずっと続けている方もいます。普段の生活ではない場面での活動をやっていると、気持ちのつながりというか、連帯感がありますね。
(司会)長く活動を続ける理由はなんでしょう。
(石橋)「ずっと続けるんだ」という使命感や、自分が必要とされているんだという気持ちです。自分が役に立ったと実感し、また行きたいと希望するメンバーも多いです。

初めて災害ボランティアに参加する方へ

(司会)初参加の方にとって不安ではないでしょうか。
(齋藤)出発前に研修会をしています。
どんなことをやるのか、そして心構えですね。やってはいけないことも伝えます。例えば、断りもなく動画を撮ってSNSに投稿する、被災者の敷地内での不用意な行動をするなどです。被災された方がそれを見たときにどう思うか、ということです。
研修は、現場で体験しながら解決するためのものです。
(石橋)現地のボランティアは私たちだけではないので、ほかのボランティアの方の動きを真似て、ふさわしくない行動をしようとするケースがあります。そんな時は、過去の事例を紹介するなどして、正しい動きに気づいてもらえるようフォローしています。
(齋藤)初参加の皆さんは、自分が初めてということを決して気にすることはありません。私たちスタッフも含めて、初めての方も立場は同じです。ベテランメンバーからのサポートもあるので、萎縮せず、ぜひ始めてみてください。
また、現地に行くばかりがボランティアではありません。募金や物資の送付など、いろいろなかたちがありますので、役に立ちたいと思ったら、まず、やってみることが大事だと思います。