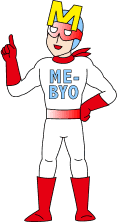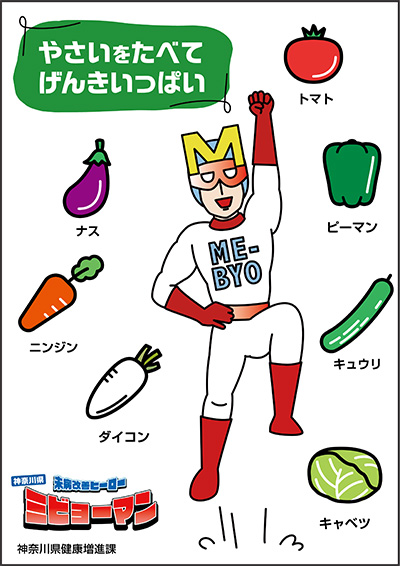ぬり絵で遊んで親子で知ろう!子どものときに身につけるといいこと
2025年7月14日
お子さんが生涯を通して、健康でいきいきと過ごすためには、子どものころに食生活や睡眠などの正しい生活習慣を身につけ、人との交流体験をもつことが大切です。ぬりえをダウンロードして、お子さんと遊びながら考えてみましょう。
野菜を食べて元気いっぱい
野菜には、ビタミンA・C、カリウム、食物繊維等が含まれ、体の中で主に次のような働きをしています。これらの栄養素を十分にとるために様々な野菜を食べましょう。
野菜に含まれる栄養素と主な働き
| 栄養素名 | 主な働き |
|---|---|
| ビタミンA |
|
| ビタミンC |
|
| カリウム |
|
| 食物繊維 |
|
かながわ健康プラン21(第3次)では、生活習慣病の予防のため、成人では1日あたり350g以上の野菜を食べることを目標としています。
食後の歯みがきを忘れずに
むし歯や歯周病は、歯にたまった歯垢の中の細菌が原因で起こります。毎日の歯みがきと歯と歯の間の清掃で、むし歯や歯周病を防ぎましょう。
健口(けんこう)かながわ5か条+3
幼児期は正しい食べ方や、食習慣の習得が大切です。この時期に身につけた正しい習慣は、生涯を通して「お口の健康」によい影響を与えます。(出典1)
| 1歳 |
|
|---|---|
| 2歳 |
|
| 3歳 |
|
| 4歳 |
|
| 5歳 |
|
| 6歳 |
注釈:フッ化物うがいとは、適正濃度のフッ化物の入ったうがい液(フッ化物洗口液)で、ぶくぶくうがいをすることです。(出典2) |
出典1:幼児期における歯科保健指導の手引きについて(厚労省)
出典2:フッ素でぶくぶくうがい むし歯を防ごう(PDF:1,670KB)(神奈川県)
夜はスヤスヤ 睡眠は元気のもと
睡眠には、心身の休養と、脳と体を成長させる役割があります。十分な睡眠がとれないと、肥満のリスクが高まる、抑うつ傾向が強まる、学業成績が低下する、幸福感や生活の質(QOL)が低下することが報告されています。お子さんの心と体の健康のために、適切な睡眠時間を確保しましょう。
1~2歳児は11~14時間、3~5歳児は10~13時間、小学生は9~12時間を参考に睡眠時間を確保しましょう。
睡眠不足による悪影響を防ぐために
夜ふかしと朝寝坊の習慣が長びくと、朝起きづらくなり、遅刻が増えたり、登校が困難になったりすることがあります。下記のポイントを生活に取り入れましょう。
- 寝る前や寝床のなかで、テレビ、ゲーム、スマホを使わないようにする
- 起床後から日中にかけて、日光を浴びて運動する
- 朝食をしっかりとり、コーヒー、コーラ類、エナジードリンクなどの摂取をできる限り減らす
参考:睡眠対策(厚労省)
出典3:健康づくりのための睡眠ガイド 2023(厚労省)
出典4 :Good Sleepガイド(ぐっすりガイド)こども版(厚労省)
いっしょに体験しよう
子どもは、身近な人や自然等との関わりの中で、主体的に学び、行動し、様々な知識や技術を身に着けます。
幼児は、子ども同士での遊びなどを通じ、豊かな想像力をはぐくみ、自分と違う人の存在や視点に気づき、相手の気持ちになって考えたり、時には葛藤したりします。自分の感情や意志を表しながら、他者と協力した学びを通して、自己の発揮と他者の受け入れを経験していきます。(出典5)
また、青少年教育研究センターが行った「子供の頃の体験がはぐくむ力とその成果に関する調査」によると、家庭・地域・学校での「体験量」と「へこたれない力」との関係は、子供の頃に下記の経験をした人ほど、「へこたれない力」が高い人の割合が高くなる傾向が確認されています。(出典6)
- 家庭での「基本的生活習慣、お手伝い、家族行事」
- 地域での「公園や広場で友だちと外遊び、友だちの家や自宅で友だちと室内遊び、スポーツクラブや少年団で活動、文化系の習い事」
- 学校での「児童会・生徒会の役員、体育祭や文化祭の実行委員、部活動の部長や役員、運動系部活動」
お子さんが豊かな人間性や社会性を身につけられるように、人との交流の機会を意識してみましょう。
出典5:子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題(文科省)
出典6:子供の頃の体験がはぐくむ力とその成果に関する調査研究 報告書[平成29年度](国立青少年教育振興機構 青少年教育研究センター)